5-BM
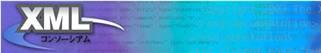
いわゆる「オライリー論文」の正式名は、「Web 2.0:次世代ソフトウェアのデザインパターンとビジネスモデル」である。技術者に対して、Web2.0的な技術開発やサービス提供の「デザインパターン」の提示を試みるとともに、経営者やサービス運営者に対して、「ビジネスモデル」の考察、刷新を迫るものとなっている。
では、Web 2.0のビジネスモデルとはいったいどんなものなのだろうか? それ以前にそもそもビジネスモデルとは何だったのであろうか? 本節ではこれらの疑問に順に答えていきたい。
企業、団体がどのような事業活動をするかのモデルである。通常は営利法人について語られるが、非営利法人にもビジネスモデルは存在する。非営利法人とは、たまたま収支をバランスさせるように運営する組織であって、高額の給与を得ている専従者がいる場合もあるし、収入面で利益率の高い事業を展開している場合もあり、効率性の追求や技術革新のニーズなど、本来は営利法人と同等の要求が存在するはずのものだからである。
上図に示したように、この事業活動のモデルは大きく3つのモデルからなる。事業体の存在意義、社会に対する使命、活動目的に照らしてビジネスの大枠での着眼点を現す戦略モデルと、それを実現する具体的なオペレーションを記述した業務モデル(BPM: Business Process Modeling)、そして、収益モデル、の3つである。戦略モデルはターゲットとなる顧客(市場)を定義し、競合との差別化戦略につながる付加価値の内容を構造的に記述したものである。業務モデルは、その戦略を実現するための業務プロセスを描き出し、個々のプロセスにおけるオペレーションの内容、その実行方法、そして、これらの体制やプロセスの設計・構築手法を描いたものである。IDEFやUMLなど様々な手法で形式的記述が試みられているが、なかなか真に有用な表現手法は現れないようである。
狭義の「ビジネスモデル」とされることもある収益モデルは、事業活動の利益を確保する仕組みである。売り上げ拡大のための収入モデルと、原価・経費節減のためのコストモデルとからなる。1事業体だけをみて収支のモデルを描くだけでなく、その事業体につながる複数のステークホルダーとの間の結線上を、どのように具体的にお金が動くか、あるいは無料で何らかのアクションが行われたり物流、情報流が発生しているかなどを含む、全体のヴァリューチェーンを描いてみないと、通常、最適化の方略、処方箋は書くことはできない。次節では、Webサービス(WebAPI)提供者を中心とした、様々なWeb 2.0の収益モデルの類型を描いている。
課金モデル (このモデルの変更にユーザが参加!):
いろんな種類の従量制へ。
でも「使い倒した方が得」という階段関数的な特徴は残す。
シンプルだけど細粒度へ。
原価積み上げでなく御利益や相場で料金決定。
バリュー・チェーン、Stakeholder間フロー(3者以上が必須):
ユーザ参加 (CGM, 従来コスト高かった売り手や仲介役,サービス生産への参加) 。
ガチガチの業界規格でなくオープンで無料のREST API等。
実質的な連携はメタデータにより遂行。
コストモデル 〜原価積み上げは終焉:
徹底した低コスト追求&同じ仕組みで高度なスケーラビリティの遺伝子を最初から組み込むこと e.g. youtube;参入障壁を徹底的に低く:「まず無料」は当然。
広く浅い大量のトランザクションを激安コストでさばく。